心理学を学んだり、社会学的な現象や原因を学んだ時
「あ〜、こういう理由で、人間関係がうまくいかなかったんだ」
と知り、納得して「これからは問題を理解できたから大丈夫だ」と安心すると思います。
私に罪悪感があったから、あの人に怒っていたんだね。
私が彼を責めていたのは、私の投影だったのね。
私が親からあんなことをされたのは、私が原因だったのね。
そのように理解して、
「これからはきっと大丈夫」
「私が怒らなければ大丈夫」
「私が寛容になれば良いんだ」というように決意し、
時間を過ごすでしょう。
しかし、しばらく経つと「怒らないなんて無理」「私は我慢できない」
「私は献身的に動いてるつもりなのに何も感謝がない」などと
リバウンドするかのように、
腹が立って仕方がない事態にまで陥ったりします。
私たちは心理学的な原因について理解できていたとしても、
その問題の対処には、そのアプローチ方法を知る必要があるようです。
問題や原因を取り除こうとするやり方では解決できない
心の問題でなかった場合、
例えば、学校や職場で問題となる出来事が発生した時、
学校であれば原因となった遊具や遊びを禁止してみたり、
人と人なら接触禁止をしてみたり、
なんらかの罰則をもうけたりして問題が再び起こらないように対処します。
職場でも似たようなもので、
なんらかの禁止、罰則、なんらかの制度や物の
撤廃をすることによって対処するでしょう。
普段からそういった権威のある第三者の介入によって
物事を解決してこようとしている様を見て育っていると、
それを家庭やプライベートの人間関係、
知人との人間関係にも利用したくなります。
というか、その方法しか知らなかったりするんですね。
何かあれば、
法律や警察などの第三者を頼る人は
その傾向が強いと言えます。
もう少し軽度であれば、友達や知人を巻き込み
「この出来事の主張は私が正しい」と多数決方式を取ろうとします。
私たちは本当の意味で当事者同士の問題を解決する方法を知ってこなかったのです。
- 権威のある第三者によって仲裁を受ける(親・先生・会社など)
- 法律などの公式の判断基準で裁く(警察・裁判など)
- 身近な第三者を含めた多数決でどちらが正しいかを決める
- 話し合いで解決したつもりで何度も喧嘩を繰り返す
- 離れる・別れる・絶交することで問題が起こらないようにする
- 別の問題に気を取られているうちに問題ではなくなる
これらのような手段で問題解決したことにしてやり過ごしてきたと思います。
学校では先生が子供同士の揉め事に介入し、
無理に謝らせた上で、無理に謝罪に納得させるような
やり方をしていることが当然になっていました。
お互いの話し合いでは解決できず問題が続くために
法律的な権利を主張してみたり、
そういったことも含めて困るので問題を隠蔽したり、
ただ被害者が離れたり、引越し等の手段を講じる羽目になったりします。
仕事では職務的な権威である上司の命令だからということで
部下に言うことを聞かせようとするとか、
異動やプロジェクトを分けることで
合わない人同士の揉め事を起こさないようにしてきました。
今はそれでは若い部下は辞めるので、
直属の上司とミーティングなどの時間を取ったり、
悩みを聞いたり、様々なケアをしているかと思います。
プライベートも嫌な人がいたら別れる、関わらない、
離婚する、喧嘩を繰り返してそのままにしているかもしれません。
自分が終わらせるという選択をしていく
問題を解決しようとするとき、
問題を俯瞰して『ここに原因がある』と思うと、
外科手術のようにその問題を切り取ろうとしたり、
その原因を作った人の考えを改めさせようとしてしまうと思います。
それは俯瞰して考えた場合で、権威のある第三者だったり、
神様のような存在が共通しているのなら可能なことかもしれません。
「その人の言うことが絶対だ」と両者が思えるような存在がいるならの話です。
実際はそんなことはありえません。
どちらが正しいかを主張すれば、
確かに法律やなんらかの基準に引っかかることをした側に問題はありますが、
法律には引っかからないが嫌がらせを
繰り返し行なっていた相手は何も悪くないのか?という
話になってしまいます。
いじめられた側がいじめっ子を殺したとなったら、
それはいじめられた側が法律的には犯罪を犯したことになりますが、
それまでいじめた側は悪くないとは言えませんよね。
犯罪を犯した人は裁かれるということは
社会のルールなので相応に罰を受けなければなりませんが、
問題を作ったのはいじめっ子の方にも原因がありますよね。
おそらく、いじめる側もいじめている相手に対して
なんらかの理由を持っています。
単に相手が肉体的に弱かったり、
何か恥ずかしいことをしたのを見られたり、
こっそり悪さをしたり、一人でいることが多いという
大したことのない理由かもしれませんが、
誰でもいじめてきたわけでは無いはずです。
私たちが人同士で問題を解決していこうと思う場合、
原因は結果を生みますし、原因探しを繰り返していても、
原因探しが続くだけです。
双方になんらかの小さな過失や原因があり、
問題が起きているのが現在の結果なのであれば、
どちらかが何かを変える必要が出てきます。
その時に相手の特定の考えや行動が悪いと責めても、
責められた相手はそれも心理的な問題によって反発し、
変わることはありません。
たくさんの小さな原因がドミノ倒しのように連なった結果が今なので、
どこかで問題を終わらせるには自分がその原因を作らないことを
選択することができれば、自分の問題にはならないはずです。
自分のために自分の怒りを手放す
喧嘩の原因の一つとして、
「相手が悪いのに、なぜ私が変わらなければならないの?」と
思う心理があります。
確かに原因が相手にあると思うと(思えるので)、
自分が相手に仕返ししたり、復讐しないのは相手にとって
得じゃないかと思ってしまいます。
だからこそ、しっかりやり返さないと気が済まないと思い、
やり返した分の反撃としてまた攻撃されたりします。
もし、反撃するような性格ではない人の場合、
攻撃されているのは自分のせいだと思い自分を責めたり、
誰にも相談できずに我慢してしまったりします。
その場合は反撃していないので、
倍返しされるということは起こりませんが、
それでもいじめのような他人からの攻撃がエスカレートして
どんどん悪化していったりします。
このどちらのパターンでも共通しているのは、
自分が攻撃的な怒りの感情を抱いているということです。
前者は相手に持っており、
後者は自分に対して攻撃的な感情を持っています。
この攻撃的な感情そのものが新たな他人からの攻撃を
促しているとしたらどう思いますか?
この現象には2つの心理的理由があります。
- 投影
- 共感・共鳴
この2つが重なって、攻撃的な感情は伝染し、
また不要な揉め事や問題を作ることになります。
投影
心理学的には、自分が他人を見て
「〇〇されている」「〇〇と思っているだろう」というのは
投影と言われます。
心理学について聞きなれている人にとっては
耳にタコなくらいの言葉ですが、
相手がどんな理由で自分になんらかの行為をしてきたのかは
本来相手にしかわかりません。
相手に何を思ってやったのかを聞いたとしても、
言葉では嘘もつけるし、本人も自覚がなかったりします。
なので、相手がなんのために自分に対して
なんらかの行為をしたのかというのは、
自分の主観で解釈することになります。
つまり、「自分がもし相手の立場だったら、
〜〜〜と思っている時に〇〇をするだろう」ということです。
そもそも相手が何もしていなかったとしても、
自分に対して攻撃してくるかも、自分に怒ってるかもと思うのは、
自分の心が攻撃的になっているからなのです。
自分が他人からどう思われているかというのは、
自分が他人にどう思っているかというのと同じになるということです。
共感・共鳴
イライラしている人が目の前にいて、舌打ちしたり、
いかにもイライラした様子だと自分もイライラしてきますよね。
気分は伝染するし、自分の感情が他人に伝染するのです。
身近な人間だと尚更共感してしまうので、
親や兄弟、仲のいい友達ほど共感してきます。
日頃から仕事のために人間関係に気を配る人ほど、
職場の人の気分にも共感してしまうでしょう。
他人に対する攻撃の気持ちも、自分に対する攻撃や自責の気持ちも、
なんとなく周りの人には無意識に伝わっているのですね。
だからこそ、近くにいる人は自分は責められている、
自分を責めているこの人を見ていると
自分も何か責められているようで
不快な気持ちになると思っているのです。
自分が本当に何もしていなかったとして
目の前で凶暴そうに吠えてる犬がいたら
「なんで何もしてないのに吠えてくんねん!」と
自分が悪い人では無いのに悪者扱いをされた気分になってしまいます。
逆に小さくなって「きゅ〜ん」と鳴いて逃げ回る犬がいたら、
自分が悪者では無いのに、自分がその犬をいじめる悪い人のような
扱いを受けた気分になってしまうのです。
だから他人に攻撃するのも、自分に攻撃しているのも、
相手を悪者扱いしているという点で共通しているため、
周りの人たちが不愉快になってしまうのです。
自分で怒りを我慢せず手放していく
大抵の場合、
「怒っても無駄なんだからやめなさい」
「怒っても何もいいことないよ」と言われたり、
「人前で怒りを露わにするなんて大人気ない」と言われたりするため、
怒りを抑圧したり、諦めたり、我慢してしまいます。
これをすると怒りっぽい子になってしまいますし、
抑圧した怒りは無意識に溜まっていきます。
そうすると本人も常にイライラしたり、
周りもイライラする状況が繰り返されるので辛さしかありません。
そうではなく、話を聞ける人がいるなら、
その怒りについて聞いてあげることも一つですし、
何に対して怒っているのか、本当はどんなふうであってほしいのか、
怒っている理由について明確化してあげることです。
怒っている理由がどんなものであれ、
その理由を気づいて認めることができた時に
怒りは無くなっていきます。
それは誰のためでもなく、自分のためにすることです。
これをすることで、自分から腹立たしい出来事は消えていき、自分の中に平和がやってくるのです。
常に自分が当事者として心理法則は働いている
誰かが仲裁する場合でも、当事者同士で話し合う場合でも、
常に心理的な法則が働いています。
なので、誰が何を発言しても、
投影と共感は常に働いているので、
当事者の一方を正しいとすると他は間違っていることになりますし、
法律的な力で解決する場合でも、間違っているとされたり、
却下された側は不満を持ち続けることになるでしょう。
自分が当事者だとしても、
仲裁者だとしても、やることは同じです。
誰も悪者にしない、誰も裁かない、
自分の投影だと思って
自分の持っている思いを見直すことです。
自分の目の前で起こっていることは、
大なり小なり、自分の投影なので、
自分が誰かと喧嘩していても、
誰かと誰かの喧嘩を自分が見ていても同じなのです。
今回はいじめや喧嘩の場合を例にしてみましたが、
何が起こっても自分が変われば周りが変わっていくのが現実です。
自分が変わっていけば、
自分の周りで起こる問題や悩みも徐々に消えていきます。
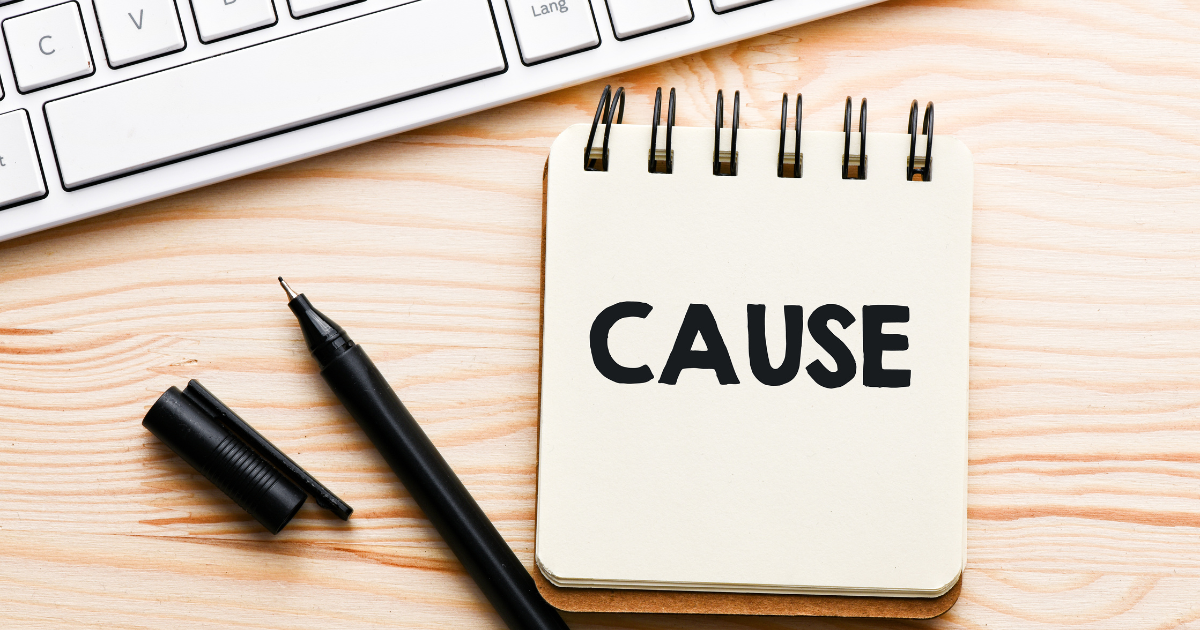
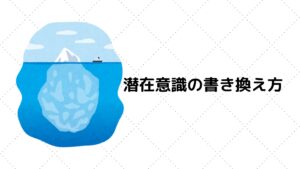





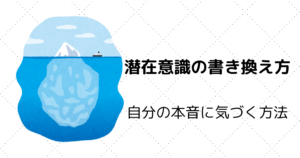

コメント